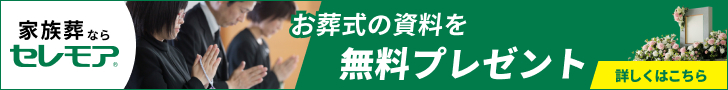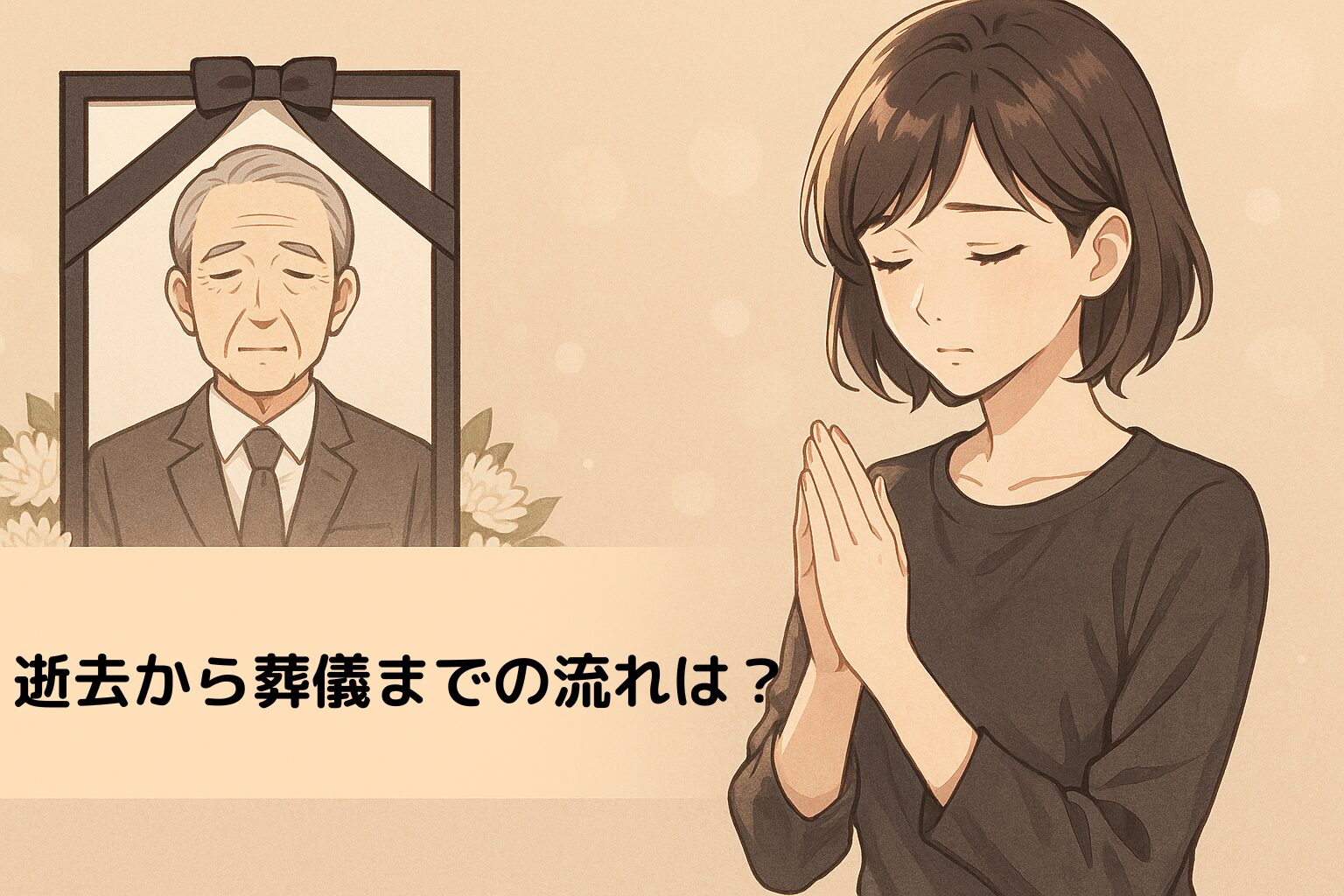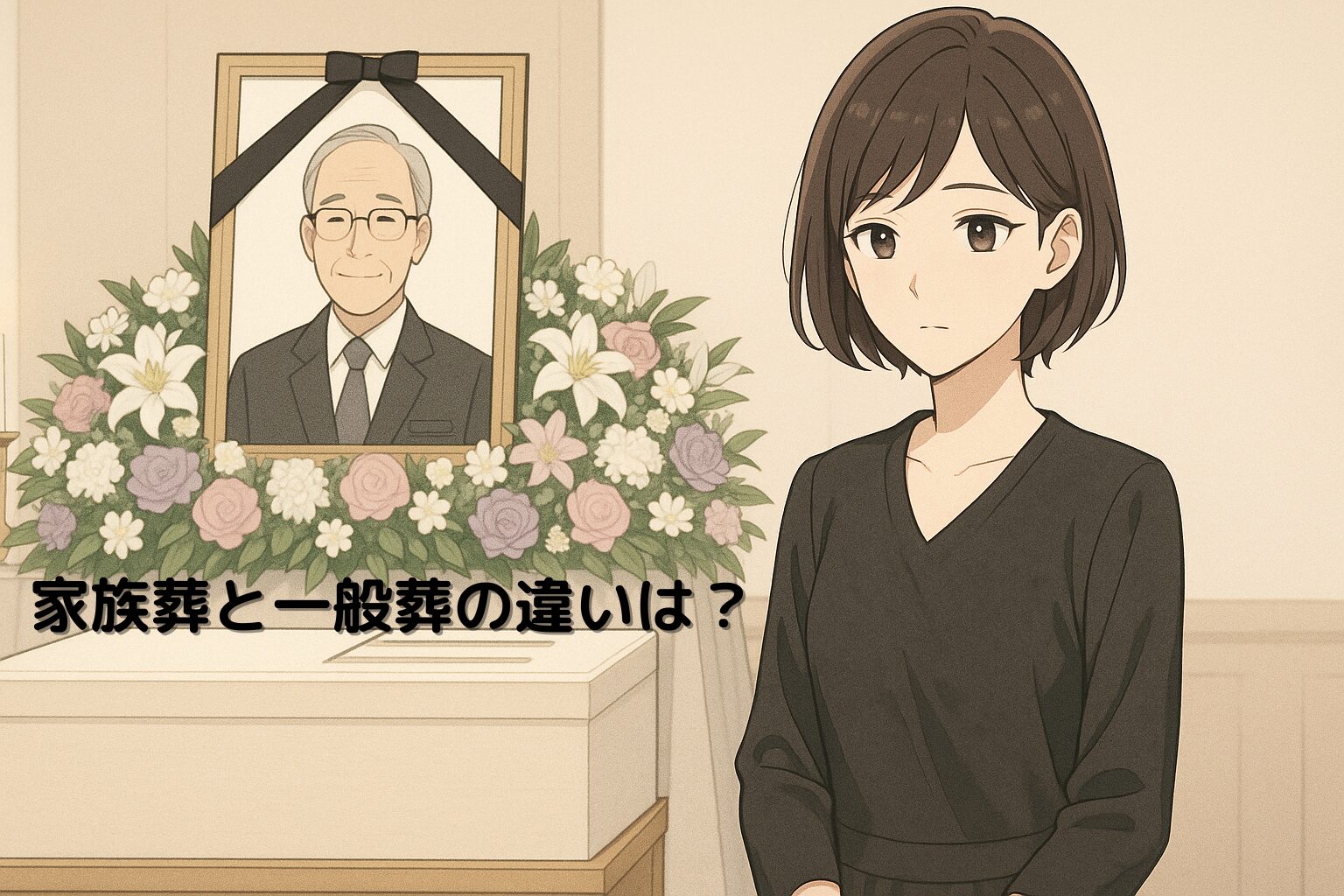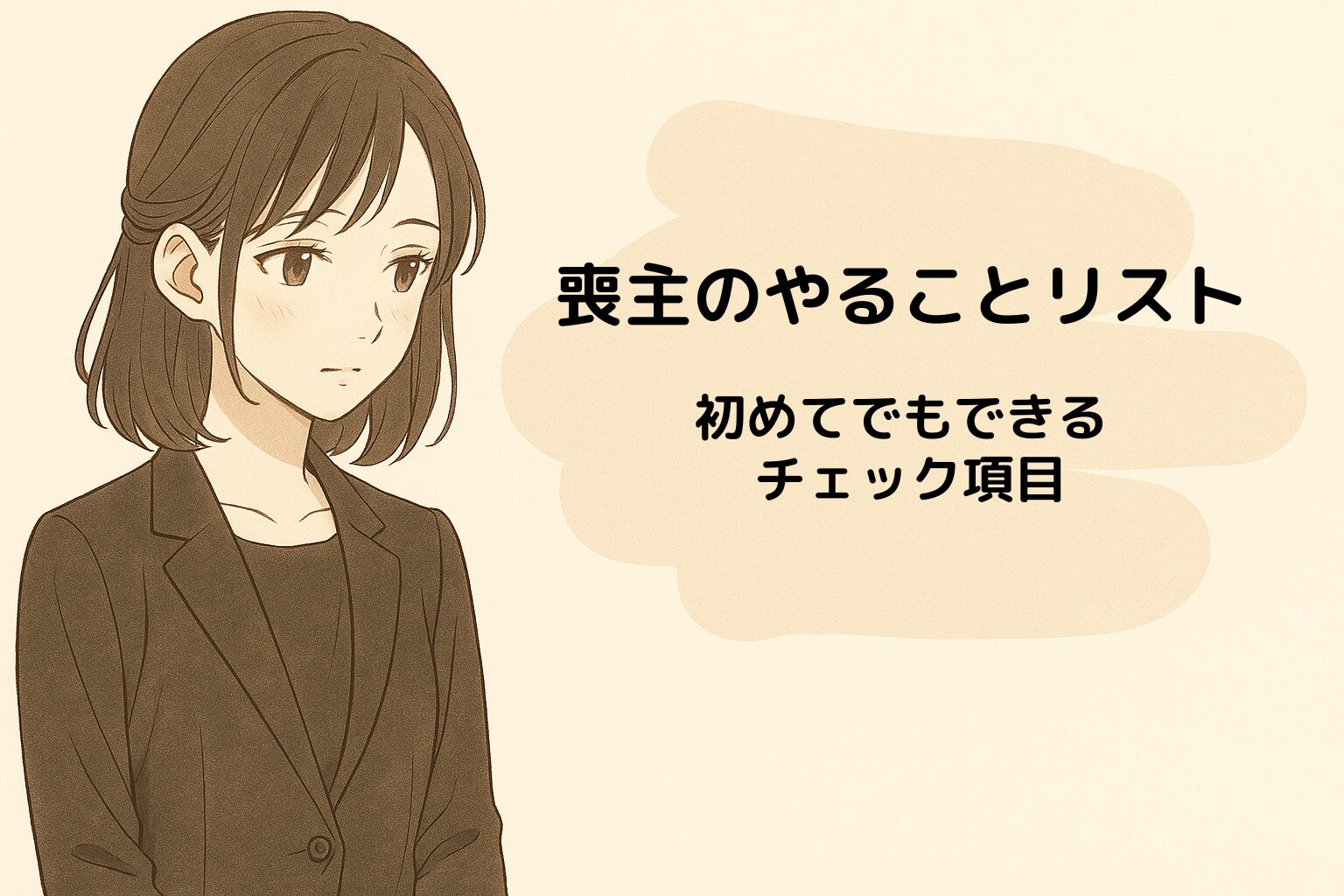死亡後にやる届け出リスト|いつまでに?どこへ?をやさしく解説

はじめに|「何を、いつまでに届け出ればいいの…?」
大切な人が亡くなった後、
葬儀だけでも大変なのに、役所への手続きも山のようにあります。
- いつまでに届け出が必要?
- どこの窓口に行けばいいの?
- 書類はなにがいるの?
この記事では、死亡後に必要な主な届け出や手続きを、わかりやすく一覧で整理しました。
「とりあえずこれを見れば大丈夫」と思える、安心できるリストをお届けします。
最優先で必要な届け出【すぐに対応】
✅ 死亡届(死亡診断書)
| 内容 | 亡くなったことを役所に届け出る書類 |
|---|---|
| 提出先 | 故人の本籍地・住所地・死亡地のいずれかの市区町村役場 |
| 提出期限 | 死亡を知った日から7日以内(国外は3か月以内) |
| 提出者 | 同居の親族・同居人・家主・後見人など |
| 添付書類 | 医師が作成した「死亡診断書」 |
☑ 死亡届の提出によって火葬許可証も同時に発行されます。
葬儀社が代行してくれることも多いので、確認を。
死亡後1週間以内に行う主な手続き
✅ 年金(国民年金・厚生年金)の停止
| 提出先 | 故人の住所地の年金事務所 or 市区町村役場 |
| 必要書類 | 年金手帳、死亡届の写し、本人確認書類など |
| 期限 | 14日以内(厚生年金はできるだけ早く) |
✅ 健康保険の資格喪失届
| 提出先 | 故人が加入していた健康保険の保険者(市区町村 or 協会けんぽなど) |
| 必要書類 | 保険証、死亡届の写しなど |
| 備考 | 国保なら葬祭費(5,000〜7,000円)などの支給あり |
✅ 介護保険の資格喪失届
| 提出先 | 市区町村の介護保険窓口 |
| 備考 | 介護サービス利用料の精算にも関係するので早めに |
死亡後1か月以内を目安に行う手続き
✅ 世帯主の変更
| 提出先 | 市区町村役場 |
| 期限 | 14日以内 |
| 備考 | 故人が世帯主だった場合に必要。新しい世帯主を届け出る必要あり。 |
✅ 運転免許証の返納・パスポートの返却
- 自治体の警察署(免許センター)で返納
- パスポートは原則返却不要だが、破棄するのがマナー
✅ クレジットカード・銀行口座・サブスクなどの解約
- 死亡届が受理された時点で口座は凍結されます
- できるだけ早めに解約や名義変更の手続きを
- 公共料金や携帯電話の名義変更も忘れずに
死亡後に必要な給付・申請(もらえるお金)
| 名称 | 支給内容 | 申請期限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 葬祭費(国保) | 5,000〜70,000円 | 2年以内 | 市区町村に申請 |
| 埋葬料(協会けんぽ等) | 50,000円 | 2年以内 | 被扶養者が対象外になることも |
| 寡婦年金 | 年間20万円程度 | 死亡後5年以内 | 一定条件を満たす妻が対象 |
| 遺族基礎年金 | 子がいる妻など | 5年以内 | 国民年金加入者が対象 |
| 遺族厚生年金 | 配偶者・子 | 5年以内 | 厚生年金加入者が対象 |
☑ 詳細や条件はケースバイケースなので、年金事務所・市役所で個別に相談すると安心です。
よくある質問(Q&A)
Q. 死亡届を出すときに戸籍謄本は必要?
→ 通常は死亡診断書があればOK。戸籍謄本が必要なのは、相続や保険など別の手続き時。
Q. 葬儀が終わってからでも間に合う?
→ 役所の多くの届け出は、死亡日から14日以内が目安。できるだけ早めに対応を。
Q. 何から手をつければいいか分からない…
→ まずは「死亡届」→「年金・保険の停止」→「銀行・ライフライン」がおすすめの順です。
まとめ|届け出の負担を減らすために
人が亡くなった後の手続きは、心が追いつかない中でもやらなければならない大事なこと。
でも、一つひとつやっていけば、確実に整理は進んでいきます。
- 役所での手続きは14日以内を目安に
- 葬儀社や親族に相談しながら一緒に対応を
- エンディングノートがあるとさらにスムーズ
「完璧じゃなくて大丈夫」
少しでも気持ちに余裕が持てるように、この記事が役立てば幸いです。